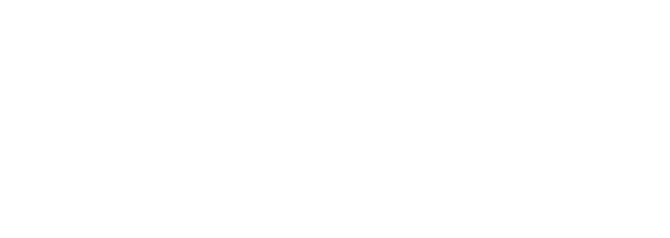音楽 鷺巣詩郎インタビュー
“安堵感”と“興奮”
二つの感情を抱く「千年血戦篇」
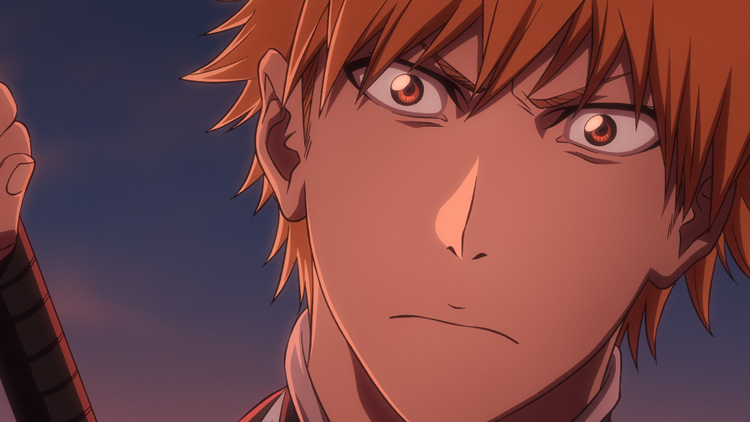
――10年ぶりにアニメ化される『BLEACH』に関わることが決まった時の感想をお聞かせください。
鷺巣氏(以下、鷺巣)
「千年血戦篇」の前のTVシリーズ、そして劇場版で9年間も『BLEACH』の音楽を作っていたので、 『BLEACH』の作業は私の中で“日常”でした。ですから、10年振りに改めてコミックスを読んだ時、そのストーリーや展開には非常にエキサイトしましたが、 同時に、絵柄やタイトルロゴを見たりした時、『BLEACH』が“日常”に戻ってきたという感覚に襲われました。
自宅に帰って来たような、我が故郷に戻ってきたような安心感、安堵感のようなものを感じたんですね。
つまり相反する二つの感情なんです。ひとつは“興奮”、エキサイティングな感覚と、もうひとつは“安堵感”、マイホームの感覚、その真逆の両面です。
――原作の中で印象的なシーンなどはございますか?
鷺巣
『BLEACH』は、動きの大きいバトルが多く、そして登場人物もたくさん登場しますが、一コマ一コマの絵で捉えると、 額縁に入れて飾りたいくらい芸術性がすごく高くてアートだと感じます。それが『BLEACH』の一番の魅力で、音楽を作る者からするとその印象が非常に強いですね。
――アニメで表現する際に音楽制作で気をつけることはありますか?
鷺巣
『BLEACH』が持つ雰囲気を壊さない、ということよりも「より拡大したい」という気持ちが大きいです。漫画で言う一コマ一コマ、アニメで言う一シーン一シーンを飾っておきたいという感覚を肥大化させる。
皆さんが『BLEACH』に何を感じるか、“独特な絵の肌触り”“空気感”、色々あると思いますが、 皆さんそれぞれが思う・感じるものを壊さないように遠慮したり、謙遜したりすると、枠の中に囚われてしまいます。
ですから、「肥大化」させようと常に思っています。漫画・単行本になくてアニメにあるのはバックグラウンドミュージックです。
漫画には音楽が鳴っていなくて、皆さんの脳内で流れている。
我々は、読者の脳内でアドレナリンが出るのを“お手伝い”するのではなく、“促進”させないといけない。
そこで“作風を壊さないように“邪魔をしないように”などの遠慮した感覚ではダメだと思っています。
ただ、「肥大化」と言っても“大きくする”だけを考えると、魅力である一コマ一コマのアート性が損なわれてしまう。
『BLEACH』のアート性を正しく拡大していくとどういう化学反応、ケミストリーが起こるのだろうと。
だからこそ音楽は起爆剤にならないといけないといつも思っています。
――視聴者にぜひ聴いてほしい曲(劇伴)をお聞かせください。
鷺巣
どの曲も自分が手塩に掛けて育てた息子や娘、そしてこれから育てていく赤ん坊のように感じるので、 比較して選ばれなかった曲がやきもちを妬くのではないか(笑)、 そんな親心があるのですが、設問にお答えするとしたら「Number One - Bankai」です。まさに今2022年の時代感覚に合うように仕上げました。
海外で感じる『BLEACH』

――音響制作の長崎さんから海外のファンも意識されていると伺いました。日本のファンと海外のファンの違いなどの印象をお聞かせください。
鷺巣
日本も海外も、ファンが自分の愛するものを肥大化させたいという“推しのスピリット”みたいなものは同じだと思っています。ただ、日本だといきなり相手に声をかけるのは失礼だと躊躇することが多いですが、 海外だと色々な職種の色々な人たちが自分なりの推しを包み隠さず表に出しているなと思います。
特に『BLEACH』の人気は世界的で、『BLEACH』を介して自分が思っていなかったような相手と触れ合える機会ができました。
それこそ、今いるフランスの田舎の市役所の職員の方から「とてもクールなアニメね」と声を掛けられたりとか、 改めて世界中いたるところにファンはいるんだと実感します。『BLEACH』の底力を肌で感じる瞬間ですね。
また、かつて英国や米国は、他の欧州や南米とは違い日本のアニメにそこまで反応しなかったんです。
どちらかと言うとゲームのほうに敏感でした。
ですが今となっては米国の、音大ではない普通の大学で、日本のアニメやその音楽を研究しているという話まで聞きますので、 日本のアニメが世界の文化としてさらに浸透したと実感します。
――制作中に起こった、印象に残っていることがありましたらお聞かせください。
鷺巣
皆さんもそうだと思いますが、2020年からのコロナによる影響はヨーロッパでも深い傷跡を残しました。レコーディングはリモートで行うことが多くなりましたし。
例えばオーケストラも管楽器を演奏する人以外はマスクを装着して演奏をする。
何十人と並んで合唱する場合も、歌わないところではマスクを付ける。作業するコントロールルーム、 この部屋も人数制限等がない場所だったのですが、4人しか入ってはいけないとか。
そういった影響がありましたが、『BLEACH』の制作が始まってからは、ヨーロッパにおいては徐々にそういうものが解除され、 今では全くなくなりました。オーケストラのレコーディングも合唱も誰もマスクを付けていないスタジオ風景になりました。
当時のマイナスな印象と同時に、昔に戻った、新しいアフターコロナの世界に入れた、そんな喜びもあります。
――ご自身のお仕事をする上で、インプットするものとして多いのは何ですか?
鷺巣
欧州で生活していると、電車に数時間も乗ればベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を、その日の夜に現地の本拠で鑑賞できますから、 それは非常に恵まれた環境だと思います。もちろん映画も観ますし、Netflix、Amazon primeなども観ます。
あと、海外で生活をしていると一日に一回クライマックスがあったりするんです。
自分で言うのも変ですが、日常生活のほうが映画的でドラマチックと言いますか(笑)。
例えば、平日の午前11時に銀行に行くとすると、絶対に営業していると思っていたら「臨時休業」の張り紙が出ていて。
そして、さすがに大丈夫だと思って次の日に行っても同じ張り紙が貼ってあって(笑)。
日本では絶対にありえないことが普通に起きます。
事実は小説より奇なりと言いますが、普段の生活自体が非常にアクシデンタルな出来事ばかりで、 毎日そういうことが起きるので、自分の生活が仕事をするうえで一番インプットできるものが多いのかなと思います。
――お仕事において、ルーティーンなどはありますか?
鷺巣
年齢を重ねて体力が落ちているので、2日続けて遠出したり、そんなことがなかなかできなくなった、しなくなりました。逆ルーティーンみたいなものですね。
とはいえ自由業ですから、 “風まかせ”な生活に変わりはありません。
“風まかせ”なれど、その“風あたり”が堪える年齢になったということでしょう(笑)。
――最近起きた/見た“因縁”、“戦い”があればお聞かせください。
鷺巣
因縁ではなく戦いで言えば、常に納期や締切に追われているので、納期・締切にまつわるものですね。『BLEACH』の場合、どんどん音楽が浮かんじゃうので、納期までに必要数を納められるかよりも、 どうやって納期までにそぎ落として納めるか、ですね。
たとえ40曲必要な場合でも僕は80曲も90曲も録っちゃうので、 40曲に絞り込む作業をしているうちに20曲しか仕上がらない…みたいな。
一つ一つ丁寧に仕上げるがために遅れちゃうことがあります。
鷺巣詩郎の原点と『BLEACH』ファンへ

――これまでの人生の中で、「ターニングポイント」、「きっかけ」となったことがございましたらお聞かせください。
鷺巣
誰々と出会ったとか、何々の仕事をしたとかのターニングポイントはなく、 生まれた瞬間がすでにターニングポイントだったと思っています。父親が漫画家、特撮作家で、自宅にアニメスタジオと特撮スタジオが併設されていて、 ガレージには馬がいたり劇中パトカーがあったり。
アニメーターが30人ぐらいいて、特撮スタジオではスタッフが火薬を使ってドンパチしている。
また、役者さんも脚本家さんも常に出入りしている…そんな環境下で育つ赤ん坊なんて絶対いないじゃないですか。
だからそういう家に生まれたこと自体がターニングポイントだったんです。
当時は何も感じませんでしたが、今考えると子供にとってこれほど幸せな環境って普通ありえないですよね。
物心がついたときには漫画を描いていました。
――小さいころに描かれた漫画はオリジナルの物語ですか?
鷺巣
そうです、小学生くらいのときは劇画調のスポーツ漫画のようなものを描いていました。それから中学生や高校生になると、それまでとは逆にギャグ漫画を描きたくなって描いたり、 女の子の気を引きたいとか色々な理由があって少女漫画っぽいものを描いたり。
そのときに描いた作品は結構自信作が多かったのですが、今は残っていなくてちょっと寂しいです(笑)。
――これからの放送に向けてファンの方々に向けてメッセージをお願いします。
鷺巣
以前とは違い、今ではSNSで世界中の人たちと瞬時に繋がれるのが大きいと思います。ファンの皆さんが自分の抱いた印象だったり、希望、願望だったりをすぐに発言できる、素晴らしい環境だと思います。
よりアグレッシブなファンは強く関わりを持とうとすれば我々と触れ合うことも可能です。
昔ながらにリアタイで毎週TVを楽しみに見るファンもいれば、電車などでスマホで見るファンもいる。
そうした多様性のある時代に、ファンと多面的に密接になれるようになったことがとても嬉しいです。